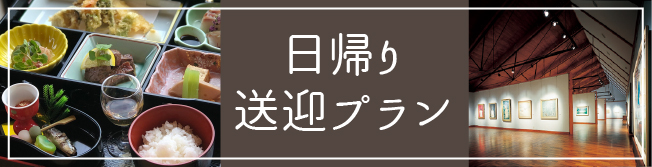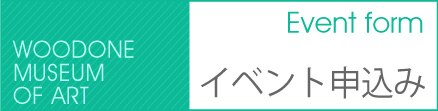過去の展覧会
2025年
アルフォンス・ミュシャ展
チェコに生まれたアルフォンス・ミュシャ( ムハ) は、19世紀末から20世紀初頭のアール・ヌーヴォーを代表するアーティストで、その優美な植物模様や美しい女性像を描いた彼の作品は、今日でも世界中で愛され続けています。
本展では、ミュシャの初期の挿画作品から、世紀末のパリの街角を彩ったポスター、室内装飾用のパネルなど、代表作の数々を紹介しました。
さらに、美術を志す若者たちに向けて出版したデザイン集や、絵葉書、カレンダー、切手、紙幣、香水ラベル、菓子箱など、デザイナーとして手がけた多様な作品・資料を一堂に展示しました。現代のマルチクリエイタ―の先駆けとも言えるミュシャの多彩な仕事ぶりを約400点の作品を通して余すことなくご覧いただきました。
お菓子の美術館
樹脂製のクリームやケーキ、マカロン、アイスクリームを用いた「Fake Cream Art(フェイククリームアート)」という独自の技法により、カラフルで精巧なスイーツアートを制作する渡辺おさむの展覧会。
幼少期より、製菓学校の講師をつとめる母親のもと、甘やかなお菓子の香りに包まれて過ごした渡辺にとって、スイーツ(お菓子)は自身の幸福な記憶の象徴であり、創造の源でもありました。到底お菓子とは結びつかないようなモチーフでさえ、渡辺の手にかかれば、たっぷりのクリームに装飾された独創的なアートに大変身!時にダイナミックで時に繊細、斬新な可愛らしさを湛えた唯一無二の表現世界が国内外で高い評価を得ています。
本展では、海の生き物や森の動物たち、ドレスや家具テーブル、そしてモナ・リザやルノワール、ファン・ゴッホ、伊藤若冲らの名画を題材とした約100点を展覧いたしました。当館収蔵の岸田劉生《毛糸肩掛せる麗子肖像》をモチーフにした新作も初公開となりました。また「もみじ饅頭絵巻」コーナーでは、広島を代表する銘菓がめくるめくアート作品に生まれ変わりました。これまでの常識や価値観を覆す作品の数々、かわいい!だけじゃない、ラディカルな芸術性で観る者を魅了する渡辺おさむの甘くて幸せな空間をご堪能いただきました。
~絵画、工芸、ガラスの装飾美~
日本美術の長い歴史に通底する美意識として、「装飾性」が大きな特徴として挙げられます。装飾とは、「装い」「飾る」という意味の漢字で構成され、<decoration>や<ornament>を翻訳するために幕末から明治期にかけて使われるようになった言葉です。日本美術の大きな特徴として、輪郭線で形を捉えたり、限られた数の色で彩色を施したり、また、背景を余白として残したりと、物の実相を写し取るというよりも、その姿を平面的に描き表している点が挙げられます。この表現方法は、陰影のついたヨーロッパの写実的な絵画と比べると、物の色や形が単純化されることで、理想的な美しさが追求され、その独特の画法が、「装飾的」と言われるゆえんとなっています。もちろん、装飾性は日本美術の特色というだけではありません。世界中どこでも、人々は衣服を装い、家をインテリアで飾ります。「装い、飾る」行為は、私たちの心を豊かにし、そしてその行為自体が、芸術の根本のひとつを成していると言えるのではないでしょうか。
本展覧会では、「装い」「飾る」ことに着目し、日本美術の装飾美を代表する円山応挙や竹内栖鳳、横山大観の日本画や、上村松園、鏑木清方、伊東深水など、美しい着物を身にまとった美人画、フランスで邸宅を飾る家具や花器を制作したエミール・ガレの作品、そして昨年新たに収蔵された葉山有樹の装飾性豊かな工芸作品など、ウッドワン美術館のコレクションを約90点展覧いたしました。装い、飾ることを楽しんできた人々の営みに想いを馳せ、その豊かな実りをご堪能いただきました。
~つくることは生きること~
株式会社ウッドワンでは、障がいのある方の雇用促進と活躍の場の提供を目指し、創作活動を応援するone's art プロジェクトを推進しています。
今回の展覧会では、広島県内で創作活動をされているたくさんの作家に出品協力いただき、才能あふれる作家のバリエーションに富んだ表現をご覧いただきました。
2024年
光の芸術家 ゆるかわふうの世界 宇宙の記憶
世界初!オリジナル技法の「光彫り」によって、絵画でも彫刻でも映像でもない新しいアートを生み出す作家ゆるかわふうの中国地方初となる個展を開催しました。
ゆるかわは、東京藝術大学大学院で建築と芸術学(美術解剖学)を学んだ後、壁や床の中に埋め込まれていて、普段は人の目には触れない建築用断熱材「スタイロフォーム」に着目します。
建築模型の材料にも用いられる断熱材に凹凸をつけ、背後からLED照明を当てることで、不思議な光の世界を浮かび上がらせるという新ジャンルのパイオニアとして注目されています。
本展では、海洋の生き物や動物を力強く表した代表作をはじめ、宇宙空間や成層圏を表現した作品約30点を公開し、また、本展開催に合わせた新作を発表しました。展示室が光の色彩に染まる、幻想的かつ神秘的な体験をお楽しみいただきました。
今にも動き出しそうな可愛らしい生き物たち。彼らは捨てられる予定だった古紙ダンボールを使って制作されています。造形作家・玉田多紀がダンボールを素材に選んだのは学生時代。気軽に手に取れ、創作の楽しさを味わえるという理由からでした。全身を使ってダンボールを丸め、制作しやすいように柔らかくしたり、水につけて解体したりと、ダンボールという一つの素材から粘土や絵具を作り、無限の可能性を引き出しています。
スケールの大きな玉田の作品は、その迫力で見るものを圧倒すると同時に、皮膚の質感や瞳の輝き、顔の表情など、細部の繊細な表現によって人々を魅了します。近年は、絶滅危惧種の生き物たちを数多く制作し、環境問題や社会問題など、現代を生きる我々が直面する課題をテーマに作品を発表し、人々に社会の在り方や人間としての在り様を問いかけています。また、ワークショップやSNSを通して、自身の生み出したダンボール造形の制作方法を積極的に発信し、作ること、表現することの楽しさを伝える活動にも力を入れています。さらに、「0歳からの芸術鑑賞」を合言葉に、大人から子どもまで、世代を越えて楽しめる展覧会を各地で開催しています。
2023年に各地で開催した個展「造形作家 玉田多紀 ダンボール物語」は、大きな話題を呼びました。この度の展覧会では、吉和の自然を題材とした新作の「物語」を加え、さらにパワーアップした内容で玉田多紀ワールドを余すことなくご紹介しました。中国地方初の大規模個展となる本展は、見て、触れて、感じて、ダンボール造形の魅力を体感できる展覧会となりました。
ー松園からミュシャ、ガレまでー
19世紀後半に西洋諸国で巻き起こったジャポニスムといわれる日本美術ブーム。このジャポニスムを取り込んだモダンアートの流れの中で、日本と西洋の双方向の影響関係により、近代以降の日本絵画はどのような展開を示したのでしょうか。本展では、日本美術に影響を受けたミュシャやファン・ゴッホ、エミール・ガレらの作品を紹介するとともに、新しい美術思潮を踏まえ日本の風土や伝統に向き合った近代日本の画家たちの作品を展覧いたしました。
主な作家は、日本の女性美の極地を表した上村松園、鏑木清方、伊東深水、人物描写において東西両洋の美を融合させた岡田三郎助、藤田嗣治、岸田劉生、全国各地に取材し日本の風光明媚な景観をとらえた梅原龍三郎や金山平三、奥田元宋ら。明治以降、日本の美が西洋や自国をどのようにめぐって今日の芸術文化を築いていったのか、作品が生みだされた背景や、東西の文化交流を遡って見渡すことで、モダンアートの源流としての「日本の美」を再発見していただける展覧会となりました。
2023年
二つの東海道五拾三次~保永堂版と丸清版~
モネやファン・ゴッホなど、近代西洋の画家に影響を与え、国際的に高い評価を得る、歌川広重(1797-1858)。「ヒロシゲ・ブルー」と呼ばれる鮮明な藍色と斬新な構図で、今もなお世界中で人々を魅了しています。中でも、《東海道五拾三次》は、江戸の日本橋から京都・三条大橋までの旅路を描いた、浮世絵版画の最高傑作です。広重は、1833(天保4)年に出版を開始した保永堂版(はじめは僊鶴堂との合版)を皮切りに、生涯で20種類以上もの東海道シリーズを手がけました。
本展では、広重の名を世にとどろかせた保永堂版55点と、保永堂版から16年後に出版された、現存数が少なく、幻といわれる丸清版55点を一堂に展示いたしました。構図、色彩、季節など、全く異なる二つの東海道五拾三次を見比べながら、時代を席巻した浮世絵の魅力を発見することが出来ました。
猫まみれ展
国内屈指の個人所蔵家 「招き猫亭」コレクションから選りすぐりの絵画、彫刻、版画など約200点をお借りし、一挙公開いたしました。
人に寄り添い、生活に溶け込み、人生に安らぎと喜びを与えてくれる猫たち。本展では、古今東西で人を魅了し続けてきた猫の表情や姿態をバリエーション豊かに表した作品の数々を紹介しました。また、本展では、ウッドワン収蔵品の中から猫をテーマにした名品を合わせて展示しました。猫好きの人もそうでない人も楽しめる展覧会となりました。
出品作家:歌川国芳、河鍋暁齋、橋本関雪、加山又造、山口華楊、杉山寧、小林清親、藤田嗣治、横尾忠則、靉嘔、吉村大星、藪内佐斗司、ビアズリー、シャガール、スタンランなど。
~絵画の花・ガレの花~
人々ははるか昔から野山に咲く草花を愛し、その儚い命に心を寄せてきました。平安時代の歌人・小野小町の詠んだ和歌に「花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに」というものがあります。物思いにふけっているうちに年をとってしまった自身の命の短さと、あっというまに色あせて散ってしまう桜の命の儚さを重ね合わせた歌で、時代を超えて、現代を生きる私たちの胸に響いています。変わりゆく季節を惜しみ、美しい姿をとどめておきたいという心情は、いつの時代、だれの心にもあるものです。作家たちは、季節折々の草花の姿を永遠のものにしようと努力を重ね、目にも鮮やかな作品の数々を残しています。
本展では、当館所蔵の絵画作品やガラス作品を約80点展覧し、美しい花々や荘厳な樹木の姿をお楽しみいただきました。主な出展作品は中島千波や上村松篁の花鳥画、上村松園の美人画に加えて、吉村芳生の鉛筆画や、ガレのガラス作品など。さらに、この度は広島市植物公園に協力を得て、描かれた植物について、写真パネルで紹介いたしました。本展を通じて、アートと自然、双方に親しみを持っていただけていれば幸いです。
~シャガールを中心に~
絵を見る時、みなさんはどこに注目しますか?色でしょうか、形でしょうか、質感でしょうか。どれも芸術表現に重要な要素ですが、今回は特に「色」に着目して、画家がどのような色を選びどう組み合わせているのか、そしてそれを見てどんな感情が引き起こされるのか、色によって織りなされる絵画作品の魅力を探っていきたいと思います。
そもそも印象派が登場する前には、林檎は赤、レモンは黄色といった風に物には固有の色があると考えられていました。印象派の画家たちはこの固有色を否定し、光によって刻々と変わる自然界の色彩を、目に映るままに、自身が感じ取った色で表現するようになります。ルノワールやシャガール、ファン・ゴッホにとっての色彩は、身の回りの事物を再現するためだけではなく、自分の思考や感情を表現する手段に置き換わっていったのです。そして、今日では色彩学や色彩心理学といった学問の発達により、色には、人々に特定の感情を引き起こす性質があることも分かっています。
本展では、色彩の魔術師・シャガールの代表作《アラビアン・ナイトからの四つの物語》を中心に、ルノワールや藤田嗣治、岡鹿之助らの華やぎと調和をたたえた色彩豊かな作品、梅原龍三郎や林武、絹谷幸二、奥谷博らの鮮やかでパワーあふれる色彩表現を紹介しました。
生活に身近で、アート作品には必須の「色」。知れば知るほど奥深い魅力が広がる「色の世界」をお楽しみいただきました。
2022年
江上 越が問いかける近代、その地平
江上越(1994年生、千葉県出身)は、日本や中国、アメリカ、ヨーロッパを舞台に国際的な活躍を見せる今注目の若手アーティストです。海外での経験をもとに、コミュケーションをテーマとする作品を発表し続け、近年では肖像画においてその本質を問いながら絵画表現の可能性を追求しています。
江上は、さまざまな社会経済システムの問題が露呈する今日の状況を踏まえ、芸術表現を通して、あらためて日本の近代化のあり方を見つめ直そうと試みます。本展では、江上がリスペクトする近代日本の洋画家・黒田清輝や岸田劉生、安井曾太郎をはじめ、ファン・ゴッホ、ルノワールへのオマージュ作品55点とあわせ当館収蔵品11点を展覧いたしました。明治、大正の洋画家たちとの時空を超えた対話により、江上は新しい絵画表現の地平を見せてくれました。最新作と江上自らが選ぶ近代洋画のコラボレーション展示をご堪能いただきました。
やまなみ工房の宇宙
滋賀県甲賀市にある福祉施設「やまなみ工房」では現在90名の方が通い、それぞれ独自のスタイルで表現活動を行っています。彼らの制作スタイルは、一人一人異なります。寝転がったり、歌を歌ったり、自分自身をほめながら、自由に生み出される、新しくそしてどこか懐かしい世界。表現は人それぞれですが、「自分の愛する世界を求めていく」姿勢は共通しています。
美術の指導者をもたず、工房のスタッフのサポートを受けながら日々思うままに制作し続ける彼らの作品が、いま国内外で多くの人の心をとらえ、大きな注目を集めています。
それは、やまなみ工房の「社会の賞賛や評価を気にすることなく、自分の愛する世界をひたすら築くことである」というモットーが、社会的な規範や常識を飛び越える手助けをしながら、作品の受け手である私たちにも、かけがえのないものを届けてくれるからに他なりません。
本展覧会では、やまなみ工房に通う人たち37名の作品約200点とともに、作品を作る人と、それを支えるスタッフの活動をパネルや映像で紹介することで、工房の魅力をまるごとご覧いただきました。
アートとは何か、生きるとは何か、過去から続く大きな問いへのヒントが詰まった展覧会でした。
~新収蔵品とともに~
光をどうとらえるか、光の中で対象をどう描き表すかという問題は、洋の東西を問わず画家たちにとって大きなテーマの一つでした。特に印象派の登場以降は、描く対象には固有の色はなく、その色や形は、刻一刻と変わりゆく太陽の光とともにうつろうものであるという認識のもと、画家たちは光を意識しつつ描法や色彩の用い方に工夫を凝らしてきました。また人物画においては、光の反射や陰影によって立体感や量感を表現するのに加え、光と影の対比を用いて人物の内面を如何に表すか、その心理描出の探求もなされています。
本展では、コレクションの中から、「光」の表現に注目し、風景や人物をモチーフに生命のきらめきや美しさを描き出した作品約70点を展覧いたしました。主な出品作品は、岸田劉生の《毛糸肩掛せる麗子肖像》や黒田清輝《木かげ》、青木繁《風景》のほか、2021年度に寄贈・寄託された照沼彌彦の写実絵画など。
画家が見た光を想像しながら、また自らの光の記憶を呼び覚ましつつ、光と影に彩られた作品の数々をご堪能いただきました。
~松園から現代作家まで~
「美人画」とは日本画きっての人気ジャンルの一つであり、美しい女性像は時代を超えて人々の心を魅了し続けてきました。画家たちは容姿の美しさにとどまらず、描かれる人物の内面の美しさをも描こうと趣向を凝らし、仲間やライバルたちと切磋琢磨してきました。
本展では、華やかな美人画の世界を楽しんでいただくとともに「画家同士のつながり」をテーマに、師弟関係や交友関係といった作者同士の関係性も併せてご覧いただきました。
第1章では日本画における女性表現である<美人画>を中心とし、上村松園や鏑木清方といった美人画の大家から、今回初出展となる現在活躍中の美人画家・坂根輝美と、自身の内的世界を女性の姿で表現する川島優といった若手作家の作品まで幅広く展覧いたしました。
第2章では、優雅さと上品さを兼ね備えた女性像を得意とした岡田三郎助や、「乳白色の肌」で人気を博した藤田嗣治らの交友関係を紹介しながら日本洋画家たちの女性像を展覧いたしました。
さらに、特別出展として、昨年新たに収蔵されたガラス作品を同時代の西洋美術とともに展示いたしました。
2021年
江戸っ子たちの間で、爆発的な人気を誇った「遊び絵」。江戸時代の浮世絵師や版元たちが知的好奇心旺盛な庶民の為に作り出し、今なお時代を超えて愛され続ける「遊び絵」の世界を、厳選した約100点の作品によって紹介しました。
出展作家には葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳、歌川芳藤、歌川貞景、歌川重宣、3代目歌川豊国(歌川国貞)らが名を連ねました。また、影絵や判じ絵などの楽しみ方を体験できるコーナーも設け、見て、読んで、触れて、浮世絵の可能性を大きく広げたバリエーション豊かな作品をお楽しみいただきました。
※ 遊び絵とは:江戸時代に庶民の間で流行した浮世絵のなかでも、遊び心にあふれた造形が特徴的な作品のこと。
【同時開催】
お弁当インスタグラマーnancyさんの前衛弁当パネル展 第2弾
また本展では、「お弁当インスタグラマーnancyさんの前衛弁当パネル展 第2弾」を同時開催しました。
お餅アートや動くお弁当など、新作パネルを多数展示しました。小さなお弁当箱から広がる面白くて美味しいアートな世界をご堪能いただきました。
キセキのシールアート
一見すると、絵画か写真のように自然な風景として目に映る大村作品。ところが実際近づいてみると、美しく彩られた画面が、あの安価でどこにでもある丸シールで出来上がっていることに驚かされるでしょう。
大村は、油彩画で身に付けた色彩感覚や造形感覚を研ぎ澄ませ、丸シールという身近な素材で誰もが楽しめる表現を追求します。それらは写真や絵画と見紛う高い再現性を持ちつつ、生々しい手作業の痕跡や素材の物質感を残し、美しさの中に違和感やギャップをはらんだ表現で観る者の視覚を刺激します。
本展では、シールアートの開拓者として新たな挑戦を続ける大村の最新作や、夜景、花、ステンドグラスなどの代表作約20点を展覧しました。
【同時開催】
鑑賞入門第11弾 アートのワザと美
また本展では、「鑑賞入門第11弾 アートのワザと美」を同時開催しました。この絵、どうやって描いたの?この置物、何でできているの?アートの素材や技法が分かれば、これまで見えなかったものも見えてくるでしょう。
主な出品作家は、藤田嗣治や岡鹿之助、香月泰男といった巨匠から、前原冬樹、奈良美智、吉村大星らの現代アーティストまで。収蔵品の中から選りすぐりの約50作品を展覧しました。
~劉生、松園を中心に~
本展では、開館25周年を記念し、当館コレクションの中でも特に人気の高い横山大観、速水御舟、上村松園、片岡球子、黒田清輝、岸田劉生、青木繁らの作品をはじめとする近代日本絵画を中心に、「風景の中へ」「いろいろな人のかたち ~あなたは誰?~」「小さきものたち」「異国へのあこがれ」といったテーマ別に紹介しました。
また、藤田嗣治の全長9mを超える大壁画《大地》や、日本人画家たちに影響を与えた西洋人画家ら、ファン・ゴッホ《農婦》、ルノワール《婦人習作》《花かごを持つ女》を同時公開しました。
展覧会の案内役は、オリジナルキャラクターの麗子ちゃん。当館のコレクションである《毛糸肩掛せる麗子肖像》の作者・岸田劉生の愛娘です。洋画家である父ゆずりの感性で、作品のことなら何でも知っている麗子ちゃんが、アートビギナーにも分かりやすく解説しました。
~はじめまして、ときめきの春~
本展では、横山大観や川合玉堂、横尾芳月、中島千波らが描く桜の名画とともに、伊藤若冲や河鍋暁斎らの初公開作品を展覧しました。この他にも、目黒雅叙園の壮麗な空間を彩った美人画や花鳥画、近年寄贈された西田俊英、其阿弥赫土の新収蔵品を、周辺作家の作品と合わせてご紹介しました。
2020年
~大観、劉生を中心に~
自然を愛し、描いた画家たちの作品約60点をウッドワン美術館コレクションの中から紹介しました。緑豊かな吉和の森の美術館で、名画鑑賞をお楽しみ頂きました。
出品作家:横山大観、菱田春草、黒田清輝、岸田劉生、藤田嗣治、ファン・ゴッホ など
― 自然への祈り ―
国内外で人気を集める新進気鋭のアーティスト小松美羽。
西日本初の個展となる本展覧会では、初期の銅版画から、近年取り組む神獣をモティーフとした作品まで、その代表作を一堂に展覧しました。本展のテーマとなる「祈り」には、いにしえから連なる自然界や生き物たちの生命に思いを馳せ、神獣の姿形を描くという行為によって、見えない世界と現世を繋ぐ媒介者であろうとする小松自身の願いが込められています。
コロナ禍において、なお一層人の心や魂を癒すために絵を描きたいとキャンバスに向かう小松の表現世界をご覧いただきました。
― 小松美羽 略歴 ―
1984年長野県坂城町生まれ。女子美術大学短期大学部在学中に銅版画の制作を開始。20歳の頃の作品《四十九日》は、際立つ技巧と作風が称賛され、それをきっかけにプロの道を切り開く。2014年には出雲大社へ作品を奉納、自らの制作テーマを一段と昇華させた。2015年、石原和幸 (庭園デザイナー)との共作で「チェルシー・フラワー・ショー」(ロンドン)へ有田焼の狛犬作品を出品、受賞作が大英博物館へ収蔵されるという快挙を成し遂げる。
ワールド・トレード・センター(ニューヨーク)にも作品が収蔵されるほか、アジア各国で個展・ライブペインティングを行う など多方面で国際的な活躍をみせる。2020年、日本テレビ「24時間テレビ」のTシャツデザインを手がける。
SouMaの美しき世界展
すべてが1枚の紙で作られた驚異の立体切り絵
白い紙が織りなす美しく神秘的な造形。切り絵作家SouMa(ソウマ)が生み出す作品は、1枚の紙から切り取られたとは思えないほど繊細で立体感に富んでいます。その技法は、白い紙にカッターを走らせ、SouMa自身が思い描いているイメージを二次元、三次元の立体造形として切り出し組み立てていくもの。まさにカミワザともいえる技法を駆使し、花や風景、人物、宝飾品などをモティーフとした豊かな切り絵表現を展開しています。本展では、SouMaの代表作や新作約40点を一堂に集め、その驚異の技と美をご紹介しました。
― SouMaプロフィール ―
松江市出身・在住。小学生の頃から切り絵をはじめ、師匠や先生を持たず独学で表現を磨く。下絵や設計図はほとんど使用せず、自身の感性のままに切り進める独自のスタイルを取る。またすべての作品を、切り離したり貼り合わせたりすることなく、繋がった1枚の紙から制作している。近年は大型切り絵作品による空間プロデュースや広告キービジュアルの制作など、アートディレクション活動も展開。実演パフォーマンス、切り絵教室、講演なども行っている。現在、松江観光大使を務める。
―お花見気分で美術さんぽ―
春は出会いや別れ、そして始まりの季節。暖かな日差しのもと、雪解け水で潤う大地に花が咲き、新しい生命が生まれる春。四季の中で最もエネルギーに満ちた季節として愛されてきました。本展では、そんな春にちなんだ4つのテーマー「恋人たちの世界」「旅に出よう」「季節を告げる花鳥」「お花見しましょう」―を設けて、コレクションの中から約100点を紹介しました。
はじめに、「恋人たちの世界」のテーマで、色彩の魔術師マルク・シャガール(1887-1985)が手がけたカラー・リトグラフの傑作挿画集『ダフニスとクロエ』を展覧しました。また、イスラム説話集に材を取った『「アラビアン・ナイト」からの四つの物語』と、その工程版画を特別公開しました。そして、春は旅立ちの季節。「旅に出よう」のテーマでは、様々な国や地域が描かれた風景画を紹介しました。このほか、四季を彩る花鳥画や、春の行楽を描いた美人画など、新しい季節にぴったりの日本画をあわせて展覧しました。
本展は5月24日(日)までの会期を7月5日(日)まで延長するととともに、5月26日(火)からは展示作品の一部(軸や屏風約20点)を入れ替え、初夏にふさわしい爽やかな作品を紹介しました。
本展の主な出品作家:
シャガール、ユトリロ、ルオー、マティス/岡鹿之助、佐伯祐三、梅原龍三郎/
歌川広重、川合玉堂、上村松園 など
2019年
~大観、松園を中心に~
「くらべる」をキーワードに、横山大観や上村松園らの近代日本絵画、ファン・ゴッホやルノワールなど近代洋画の魅力を幅広くご紹介する鑑賞入門第11弾が開催されました。
画業の初期と晩年の作品をくらべることで、若き日の葛藤や画家が追い求めた美の境地が見えてきたかと思います。また、師と弟子が、同じ画題、同じ年代に取り組んだ作品を並べてみると、憧れの存在からライバルへとその関係を変えながらも、それぞれの画境を極めゆく画家の姿が垣間見えました。
この他、富士山や奥入瀬、瀬戸内など、同じ風景を描いた画家たちの作品を比較したり、ファン・ゴッホやルノワール、ブラマンクといった西洋の巨匠に影響を受けながら自己の表現を追求した日本人画家の作品を並べて展示いたしました。
主な出品作品:上村松園《美人之図》《雪吹美人図》《舞仕度》、横山大観《秋野》《霊峰不二》《神霊不二山》、川合玉堂《春雨》、橋本関雪《片岡山のほとり》《猫図》、藤島武二《カサ・ディ・ヴェッティ(ポンペイの遺跡)》《太陽のある風景》、熊谷守一《裸》《裸婦》、梅原龍三郎《富士山図》、片岡球子《東海道の富士》、ファン・ゴッホ《農婦》、ルノワール《花かごを持つ婦人》《婦人習作》、佐伯祐三《リュ・エルネスト》ほか約70点
浅尾省五と野生の仲間たち
この度ウッドワン美術館では、「動物写真家 浅尾省五と野生の仲間たち」を開催しました。
広島県廿日市市出身の動物写真家・浅尾省五(1948-)。幼い頃から動物や機械の修理が大好きだった浅尾は、中学時代からカメラで身の回りの植物や動物を撮影することに興味を持ち始めました。上京後、通信会社に勤務しながら写真家を目指し、24歳の時に、動物写真の第一人者である田中光常(1924-2016)の下で学びます。その2年後、約2年間の東アフリカ駐在勤務をきっかけに本格的な野生動物の撮影を始め、動物写真家に転向してからは、北極、南極、熱帯、亜熱帯と広範囲にわたり取材を続け、世界中の野生動物を撮影してきました。
本展では、浅尾がおよそ45年に亘り野生動物たちを撮影し続けてきた膨大な写真作品の中から、写真人生の原点となったアフリカ大陸をはじめ、北アメリカ大陸、そして 故郷・日本という地域に焦点を当てつつ、約70点を精選して紹介しました。野生動物の本来の生息環境を見ることが活動の源と浅尾自身が語るとおり、懸命に生きる動物たちの命の一瞬の輝きをとらえた写真ならではの臨場感を感じていただけたら幸いです。
地球上にともに住む仲間である野生動物たちが美しく、けなげに生きる姿を展示いたしました。
どこから見ても本物にしか見えない…その精緻な技巧を超絶技巧と評される前原冬樹。一つの木の塊から細密にもののかたちを彫り出し、油彩で質感や風合いを表現することで、懐かしくも失われゆく風景や、ものの朽ち果て際の美しさをモチーフに作品をつくり続けています。
1962年、東京都に生まれた前原冬樹は、プロボクサーとして10年ほど活動した後、32歳で東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻に入学。卒業制作として絵画と木彫による半立体の作品に取り組んだことを機に、以後、独学で木彫の道を歩む、異色の経歴を持つ作家です。
錆び付いた非常階段にそっと置かれた小さな折り鶴、使い込まれた自転車の皮のサドル、皿にぽつんとのせられた梅干し…前原冬樹ならではの感性によって生み出されるそれらの作品をじっと見つめていると、心に降り積もった記憶のかけらを凝縮した風景が鮮やかによみがえってきます。
本展は、前原冬樹の初期の作品から最新作まで約40点をご紹介する、西日本初の本格的な個展を開催いたしました。
~エミール・ガレ、ミュシャを中心に~
アール・ヌーヴォーは、19 世紀末のヨーロッパを席巻した美術運動です。華やかな装飾で知られるアール・ヌーヴォー様式の芸術は、花や自然界の生き物を有機的な曲線で表現する日本美術の影響を受けて大きく花開きました。 本展では、アール・ヌーヴォーを代表するエミール・ガレの木製家具や、アルフォンス・ミュシャのポスターの他、花や美しい女性に題材を求めた日本美術の粋をご紹介いたしました。
2018年
華やかな色彩と、自身の人生の物語や故郷の風景を主題とした作品で知られ、いまなお世界的に愛好されている芸術家マルク・シャガール(1887-1985)。
シャガールがはじめて手がけたカラー・リトグラフによる版画集『「アラビアン・ナイト」からの四つの物語』(1946年〈1948年刊〉)は、「千夜一夜物語」の名前でも知られる中世イスラム世界で編まれた説話集の中から、シャガールが四つの物語を選び、印象的な場面を絵画化したものです。本展では、完成までに重ねられる段階のすべての試し刷りが添えられ、普及版には付されていない13番目の作品がそろった特装版を公開。シャガールのカラー・リトグラフの最高傑作として名高い絢爛たる色彩を誇る『ダフニスとクロエ』(1957-60年〈1961年刊〉)全42点とあわせて、新収蔵初公開しました。
また、モーリス・ユトリロ(1883-1955)や藤田嗣治(1886-1968)らエコール・ド・パリの画家たちの作品のほか、モーリス・ド・ヴラマンク(1876-1958)やパブロ・ピカソ(1881-1973)などパリで活躍した画家たちの作品もご紹介いたします。藤田嗣治の壁画《大地》(1934年)や、ジョアン・ミロ(1893-1983)のタペストリー《マングース》なども出品。見どころ満載の展覧会でした。
~鑑賞入門第10弾~
アートの中には秘密がいっぱい!きれいな女の人の絵だけど、どこか普通と違うような・・・。
透き通る白い肌の女性、本の中から立ち現れる足のない女性。いったい何者?描かれた人物の謎に迫るコーナーや、絵の題名を当てる「タイトルしりとり」、複数の絵に共通する言葉を見つける「キーワード探し」など、いろんなテーマでアートの世界をお楽しみいただきました。
主な出品作家は、横山大観、上村松園、黒田清輝、有元利夫、森本草介、籔内佐斗司など。会期中、自然空間をアートに変える藤江竜太郎の野外作品も公開したほか、ゆらゆら動く蝶を作るワークショップも開催いたしました。
365日エンピツ画
写真と見まがうような、いやそれ以上の現実感を湛えた独特の画世界によって、見る者に強烈なインパクトと感動を与える吉村芳生(1950-2013)。
その作品は、鉛筆や 色鉛筆を用いて、写真をマス目ごとに克明に写し取るという、まさに驚異的な手技によって生み出されています。その誰にも真似できないと思われる超絶技巧を、息子・吉村大星(1992-)は、独自の表現として深化させつつあります。主に野良猫をモチーフとした鉛筆画は、記憶や想いが時間とともに熟成し、客観的であると同時にある種のノスタルジーを感じさせるような独特の魅力に満ちています。
見るたびに新しい景色を見せてくれる吉村芳生。今まさに進行形の表現を展開する吉村大星。出品総点数は、約80点。同じ手法で異なる境地を示す吉村親子初の規模となる競演を展覧しました。
季節の情趣あふれる日本絵画展
うららかな春の日、口元に袖を寄せて散り急ぐ花をながめふと感傷にひたる佳人、春の野に出でて摘み草に興じる女性の姿、可憐かつ神秘的な趣きで咲き誇る桜の大樹…。
自然豊かな日本では、画家たちは、四季折々にうつろいゆく風物や自然の営みに美を見出し、季節を多彩に表現してきました。
本展では、横山大観や上村松園、鏑木清方、安田靫彦らの名品の中から、美人画や花鳥画、そして風景画まで、季節の情趣あふれる作品を展覧し、画家たちの個性豊かな作品をお楽しみいただきました。
2017年
もう一つの彦根屏風
彦根屏風は、江戸時代の寛永年間(1624~44)に、当時の京の遊里の様子を描いたものとされ、彦根藩主である井伊家に伝来したために「彦根」の名を冠して呼ばれています。 近世初期風俗画を代表する傑作として高く評価され、昭和30年に国宝に指定されました。
本展では、この彦根屏風と図様がよく似た縦長の大作を当館初公開し、知られざる名画の秘密に迫りました。この他、収蔵品の中から、春夏秋冬、四季の感じられる日本絵画を展覧しました。
タグチ・アートコレクションのエッセンス展
世界のアートシーンが一望できるコレクションをめざして、様々な国で注目されているアーティストの作品を加えながら、そのスケールを拡大し続けているタグチ・アートコレクション。グローバルに活躍するアーティストのマスターピースや大作が多く含まれる国内屈指の現代美術コレクションです。
本展は、タグチ・アートコレクションを西日本でまとまったかたちでご紹介するはじめての機会でした。コレクションの原点となったキース・ヘリングや、アンディ・ウォーホルやロイ・リキテンスタインらアメリカン・ポップアートの作品をはじめ、会田誠の7mにもおよぶ《灰色の山》、6mを超える鴻池朋子の《第2章 巨人》などの大作や、杉本博司、トーマス・ルフ、ライアン・マッギンレーら現代写真のトップランナーたちの美しく刺激的な作品、そして、草間彌生、ジュリアン・オピー、奈良美智、大岩オスカール、名和晃平など、国際的に活躍する国内外のアーティスト33組の作品を59点選りすぐりご紹介する、現代アートのエッセンスが凝縮された企画展でした。
倉本聰点描画展
北海道富良野を拠点に数多くの名作を世に送り続けてきた脚本家倉本聰。 「樹に履歴あり」という言葉が示すとおり、倉本聰は十数年に渡り、富良野のアトリエや旅先で周辺の樹々を見つめ、その1本1本にドラマを見出して描き続けてきました。作品は、いずれもスケッチブックに細いペン先で無数の点を打つという繊細な点描画の手法によって制作されており、その総数は600点を数えます。 本展は、倉本聰が現在進行形で描き続けている点描画から100点を厳選して紹介する初めての展覧会でした。厳しく温かなまなざしによってすくい取られた樹々や生きものたちのつぶやきに耳を澄ましてみました。
同時開催
倉本聰セレクション 絵画名品選
さらに、ウッドワン美術館収蔵品の中から倉本聰がお気に入りの作品を選んで紹介する「倉本聰セレクション 絵画名品選」を同時開催しました。 倉本聰が、自らセレクトした作品に言葉を添え、作品の 新たな魅力を紹介する貴重な企画。今夏、ウッドワン美術館でしか見ることのできない夢の競演が実現しました。
絵画に咲く女性たち
本展では、笠間日動美術館コレクションの中から女性をテーマにした油彩画70 点を展覧しました。主な出品作家は、近代日本洋画の巨匠・藤島武二や岡田三郎助、青木繁、竹久夢二、岸田劉生をはじめ、 中山忠彦や森本草介、渡邊榮一ら現代洋画壇を代表する人気作家たち約60 名。
古今東西、画家達の永遠のテーマである女性像。時代を超えて描き継がれる多様な女性美をご覧いただきました。
※当館収蔵 岸田劉生《毛糸肩掛せる麗子肖像》(1920年)も公開しました。
2016年
描かれたモデルはいったい誰?
絵の中の季節はいつ?
この風景はいったいどこ?
じつは、絵画には、いろいろな物語や意味が隠されています。絵画をじっくり見て向き合うと、絵画はあなたに語りかけるように、さまざまなことを教えてくれるでしょう。
本展では、作品を鑑賞する際の素朴なギモンにお答えしながら、コレクションにまつわる、とっておきのエピソードを紹介しました。
主な出品作品:高橋由一《官軍が火を人吉に放つ図》、和田英作《妙高残雪》、小出楢重《少女お梅の像》、藤田嗣治《ディナー・パーティー》、ルノワール《婦人習作》《花かごを持つ女》、横山大観《神国光曙》、富岡鉄斎《漁樵問答図》、下村観山《芍薬》、川端龍子《吉祥童子》、奥田元宋《秋耀淙々》など約80点
近世初期の風俗画や浮世絵の女性描写を源流として、明治以降、流麗な線描や情緒豊かな画面構成による女性像が人気を博しました。本展では、日本有数の美人画コレクター・培広庵のコレクションを中心に、明治・大正・昭和の三代に渡り花開いた美人画をご紹介しました。三大美人画家と称された、上村松園、鏑木清方、伊東深水をはじめ、大阪の画壇で活躍した北野恒富、島成園、京都で国画創作協会を設立した村上華岳、土田麦僊。大正デカダンスの画家・甲斐庄楠音、岡本神草。そして、大正ロマンを代表する竹久夢二。約60人の画家たちが女性の姿に託して描き出した美の世界をお楽しみいただきました。
また、中国地方初公開の培広庵コレクション《洛中洛外図屏風》や、ウッドワン美術館のコレクションから収蔵後初公開となる、歌川豊春の肉筆浮世絵《観桜納涼図》や尾形月耕《観桜観月図》を特別出品しました。
永井秀幸3Dアートと絵本原画展
これぞ鉛筆の力!スケッチブックと鉛筆で生み出す3Dアートの世界をご紹介しました。 紙の上に飛び出して見える不思議な絵本の原画をはじめ、永井秀幸の代表作約40点を公開。 スマホやデジカメをのぞいて不思議な世界をお楽しみいただきました。
同時開催 ~コレクション展Ⅱ~
「いきもの大集合!」
コレクションの中から、鳥や猫、犬、昆虫など生き物を題材にした
日本画、洋画、彫刻、エミール・ガレのガラス作品など約60点を展覧しました。
コレクションにドキッ!アートに夢中【後期展】
後期展では、高橋由一、浅井忠、岡田三郎助、青木繁、藤島武二、藤田嗣治、梅原龍三郎、佐伯祐三、海老原喜之助、鴨居玲、森本草介ら近現代日本洋画の秀作をご堪能いただくとともに、日本人画家たちに大きな影響を与えた西洋人画家―コロー、ファン・ゴッホ、ルノワール、ユトリロら―の絵画作品をあわせて約60点ご紹介しました。
コレクションにドキッ!アートに夢中【前期展】
ウッドワン美術館では、当館を訪れる誰もがひとつは好きな作品、お気に入りのものを見つけられるよう、バラエティーに富んだアートをコレクションしてきました。
本展覧会では、コレクションから厳選した近代日本画や近代日本洋画を中心に、エミール・ガレによる芸術性の高い木製家具やアール・ヌーヴォー様式のガラス作品、思わず息をのむ細密さの幕末・明治期の薩摩焼など、多彩なジャンルにわたるアート約170点を、前期展と後期展の2回にわけて展覧しました。
絵画作品は、前期展で、横山大観や上村松園などの近代日本画と、岸田劉生《毛糸肩掛せる麗子肖像》と吉村芳生《コスモス》を特別公開。
2015年
~鑑賞入門第9弾~
これって何で出来ているの?どうやって描いているの?絵画鑑賞入門の第9弾となる本展では、絵画をより深く味わうためのポイントをわかりやすく解説しました。
絵にはそれぞれの個性があります。線の太さや細さを変えたり、いろいろな色をぬったり…。絵筆や絵の具をどの様に使うか、さらに、どんな紙やカンヴァスに描くかによって、無限のバリエーションが生まれる絵の世界。技法という視点から絵を鑑賞することで、作品をより身近に感じていただけたら幸いです。
新館では、森本草介や野田弘志の細密画、岡鹿之助や高田誠らの点描画などを展示しました。技法的に大きく異なる作品を見比べながら油絵の奥深い魅力に触れていただきました。
東京・神田に生まれ、明治・大正・昭和の三代を生きぬいた日本画の巨匠、鏑木清方(1878-1972)。 浮世絵の流れを汲み、情趣豊かな明治時代の東京の風俗を描いた清方は、粋と品格をあわせ持つ女性像により、近代日本を代表する美人画の名手としてその名を知られています。 その清方の愛弟子・伊東深水(1898-1972)は、東京・深川に生まれ、13歳で清方に入門。以来、師ゆずりの浮世絵の伝統を継ぎ、鮮やかな色彩と卓越した描写力で、モダンで洗練された女性像を生み出していきました。
本展では、清方と深水、師弟二大巨匠の画業をご紹介しました。日本風俗画の大きな流れの中に位置付けられる二人の豊麗なる画世界をご覧いただきました。
横山大観と昭和の五山を中心に
後期展では、近代日本画の礎を築いた横山大観と、昭和の五山と称された東山魁夷、杉山寧、髙山辰雄、加山又造、平山郁夫を中心に、近現代の日本画の粋をご紹介しました。主な出品作品は、横山大観《神嶺不二山》、東山魁夷《フレーデンスボーの森》、平山郁夫《エジプトの少女(王家の谷ルクソール)》など。
新館では、ルノワール、ファン・ゴッホ、ユトリロ、浅井忠、佐伯祐三など洋の東西を代表する洋画家の約10作品を展覧する「近代洋画展 ~東西の美~」を開催しました。
藤田嗣治と日本洋画の巨匠たち
本館では、藤田嗣治と日本洋画の巨匠たちと題し、戦前のパリで一世を風靡した画家・藤田嗣治(1886-1968)と同時代に活躍した日本人画家の作品を一堂に展覧し、藤田作品を軸とした明治、大正、昭和の洋画壇の動きを紹介します。藤田の主な出品作品は、1934年に手がけた大壁画《大地》や、理想的な女性美を表した《EVE》など5点。このほか、藤田の画学校時代の師である黒田清輝の代表作《木かげ》や、藤田がニューリーダーとして影響力を持った二科会のメンバーの作品も展覧しました。
新館では、近代日本画の粋展と題し、横山大観《月》、上村松園《春》、伊藤小坡《山羊の乳》など約10点の絵画を展覧しました。
山口県出身の吉村芳生(1950-2013)は、写真や新聞を克明に描き写したモノクロの鉛筆画や、100色の色鉛筆でふるさとの自然を描いた色彩豊かな作品で知られます。その透徹したまなざしと驚異的な描写力による独自の画世界は、一度見たら忘れられないほどの強烈なインパクトをもって見る者を魅了します。 まるで命を刻みこむかのような絶え間なく揺るぎのないタッチが集積した画面は、まさしく描くことが生きることであった画家の命の軌跡ともいえるでしょう。
本展では、新聞の一面に自画像を描いた「新聞と自画像」シリーズや、東京で手がけたモノクロの鉛筆画、山口県徳地に居を移して制作した花や景色の彩色画など約40作品を一堂に展覧し、多彩な吉村芸術の魅力をご紹介しました。
2014年
画家たちが描いた我が子や家族の肖像のほか、身近な動物たちや画家がこよなく愛した故郷や旅先の情景など、「愛しきもの」が表された絵画や彫刻を中心に展覧しました。
主な出品作品は、横山大観《秋野》、児玉希望《月光》、竹久夢二《包みを抱いた娘》、高山辰雄《𠋣る》、西田俊英《彷徨-旅》、岸田劉生《林檎を持てる麗子》、安井曾太郎《農夫像》、南薫造《二人の少女》、藤井勉《新春》など。また、籔内佐斗司の童子をモチーフとした作品もあわせて展覧しました。
上村松園・松篁・淳之 美の饗宴展
~松伯美術館コレクションを中心に~
近現代日本画壇に燦然と輝く上村松園、松篁、淳之ら3人の画家の作品をご紹介。松伯美術館の所蔵作品の中から、上村松園の美人画(本画・素描・下絵など)、上村松篁、上村淳之の花鳥画を中心に展覧し、脈々と受け継がれる美への飽くなき探求の精華と三人三様の美の境地をご紹介いたしました。
ベストオブウッドワン美術館
画家たちが描いた我が子や家族の肖像のほか、身近な動物たちや画家がこよなく愛した故郷や旅先の情景など、「愛しきもの」が表された絵画や彫刻を中心に展覧しました。
主な出品作品は、横山大観《秋野》、児玉希望《月光》、竹久夢二《包みを抱いた娘》、高山辰雄《𠋣る》、西田俊英《彷徨-旅》、岸田劉生《林檎を持てる麗子》、安井曾太郎《農夫像》、南薫造《二人の少女》、藤井勉《新春》など。また、籔内佐斗司の童子をモチーフとした作品もあわせて展覧しました。
ベストオブウッドワン美術館
同、財団設立20年周年記念の春季展です。
本展のテーマは、「収蔵品の魅力再発見!」。学芸員や来館者おすすめの作品解説コーナーや、常設展示室に「蔵出し逸品」コーナーを設けるなど、コレクションの魅力を様々な角度からご紹介します。
出品作家は、日本画では橋本雅邦、横山大観、速水御舟、鏑木清方ら。洋画では、高橋由一、山本芳翠、藤島武二、藤田嗣治など。この他、鴨居玲や森本草介らの作品など、近現代日本絵画を代表する画家の代表作や来館者に人気の高い作品を一堂に公開します。また、新館では「画家 一期一会の表現」コーナーを設け、西洋人画家に影響を受けた日本人画家の作品を並べて展示。
2013年
本館:花と美人展
新館:花と美人展~日本洋画の美女たち~
春夏秋冬、巡る季節に沿いながら、花と美人を描いた日本画と油彩画を一同に展覧しました。主な作品は、美人画の三大巨匠、上村松園、鏑木清方、伊東深水の作品をはじめ、梅の精を描いた横山大観《羅浮仙》や、しだれ桜と舞妓の競演が鮮やかな横尾芳月《祇園の花》、野辺に横たわる女性に可憐な百合の花を添えた黒田清輝《木かげ》など近代日本絵画約60点です。
新館では、「日本洋画の美女たち」と題し、現代的な女性美を示す中山忠彦や森本草介の油彩画のほか、小菊を手にした愛娘を描いた岸田劉生《毛糸肩掛せる麗子肖像》を特別公開しました。
アートいきいき!元気になる絵画展
毎年恒例の絵画鑑賞入門の第8弾。今回は、「元気になる絵画」をさまざまな切り口で展覧します。
誰もが一度は絵や写真を見てワクワクしたり、心がおだやかになった経験があるのではないでしょうか?この展覧会では、絵画に描かれた色や形が人の心に与える効果に注目してみました。色々な色の中から、新陳代謝を促進する絵(赤)、リンパ系を刺激し機能を高める絵(黄)、内分泌系の働きを鎮静させる絵(青)、リラックス効果のある絵(緑)などを紹介します。また、描きかたや構図によって、見る人にパワフルな印象を与える絵画をあわせて展覧します。
本館の主な出品作品は、個性的な造形感覚をもつ片岡球子の《東海道の富士》や、華麗な色彩と豪快なタッチで知られる梅原龍三郎の《青楓煙景》、大画面に静寂の世界を紡ぎ出す牧進の《四季麗麗》など、当館収蔵品の中から選りすぐった絵画作品約50点です。
新館の絵画展示室では、「アートの中のいろ、かたち」をテーマに、色彩の魔術師として知られるマルク・シャガールが初めて手がけたカラーの版画集《アラビア夜話から4つの物語》を展覧する他、青い色が美しいアンリ・マティスの《ブルー・ヌード》シリーズや、光と色を見つめた印象派ルノワールの女性像、豊かな色彩で自然を描いたアンドレ・ボーシャンなど西洋画家の作品を中心に、約20点を展覧しました。
~海と山のコレクション~ 夢のコラボ展
蘭島閣美術館は、広島県呉市下蒲刈町という瀬戸内海に浮かぶ島にある美術館です。 日本画は横山大観などの院展作家や京都画壇の作家などを幅広く収蔵し、洋画では須田国太郎や寺内萬治郎などの秀逸なコレクションを有しています。 本展は、瀬戸内海に抱かれた蘭島閣美術館と、中国山地の原生林に抱かれたウッドワン美術館が所蔵する、日本の近現代絵画の名品を一挙にご紹介するウッドワン美術館初のコラボレーション企画です。
本館では、横山大観、菱田春草、竹内栖鳳をはじめとする往年の巨匠たちの作品から、福田平八郎、片岡球子、奥田元宋など、伝統と革新の狭間で創造を続けた日本画家たちの作品を展示しました。
洋画では、安井曾太郎、梅原龍三郎、寺内萬治郎、林武、靉光、須田国太郎や現代写実絵画界の旗手、野田弘志、森本草介らの写実の世界をご覧いただきました。
新館では「日本の華」ともいうべき、上村松園や鏑木清方、石本正らの描く、美人画ばかりを集めたコラボ展を企画しました。「こんな作品もあったんだ!」と感じることができる、そんな名品ばかりが揃い踏みの夢のコラボ展。
2012年
~描かれた日本の原風景~
本 館:描かれた日本の原風景展
新 館:異国の風景展
海やまのあいだ、実り豊かな美しい大地、四季に彩られた日本の風景。
本館では、古き良き日本の風景をテーマに横山大観の描く富士山や、川合玉堂、児玉希望、奥田元宋、梅原龍三郎らの描く自然の風景、浅井忠や向井潤吉、南薫造らの描く人里の風景などを展覧いたしました。
新館では、伝周文《四季山水図》(国指定重要文化財)をはじめ、佐伯祐三、三岸節子ら、日本人画家が描いた異国の風景画をご紹介いたしました。
~宮尾本「平家物語」の挿画と花々の宴~
本 館:中島千波 展
新 館:ウッドワン美術館所蔵
花の画家として知られる中島千波画伯は、1945年長野県に生まれ、東京芸術大学在学中より院展を舞台に作品を発表し、1979年には山種美術館賞展で優秀賞を受賞、1995年にはパリ三越エトワールで個展を開催するなど、国内外で活躍する現代日本を代表する画家の一人です。
身近な花を繊細華麗に描いた花鳥画が有名ですが、1999年から2003年にかけては、週刊朝日に連載された宮尾登美子著『平家物語』の挿画全201点を手がけ、壮大なスケールの歴史絵巻を見事に描き表して新境地を切り拓きました。
本展は、中島千波画伯の生まれ故郷、長野県小布施にある「おぶせミュージアム・中島千波館」のご協力により、宮尾本『平家物語』の挿絵原画約30点をはじめ、初期のシュールレアリスム作品から、深い精神性を湛えた人物画、みずみずしく現代的な花鳥画の数々を展覧いたしました。
ウッドワン美術館のコレクション対決!展
本 館:コレクション対決!展
新 館:女性美の競演
本展では、当館コレクションの絵画・陶磁器・ガラス工芸品の各ジャンルから代表作品を選出し、「花」「動物」「風景」「女性」といったテーマのもと、作品を対決させるように並べて展示することで、作品の類似性や違いを鑑賞してもらうことを目的とした。
絵画作品の主な出品作家は、横山大観、上村松園、速水御舟、岡田三郎助、梅原龍三郎、森本草介ら。このほか、エミール・ガレやドームのガラス工芸品、マイセン磁器、薩摩焼、中国陶磁器の中から選りすぐりの作品を展示した。
本 館:生命讃歌 ~大地と人間~展
マイセン館:ファン・ゴッホ《農婦》の真相に迫る
本展では、当館収蔵品のファン・ゴッホ《農婦》(1884-85年)に関して2011年の夏から行った現地調査や最新の科学調査(吉備国際大学との合同プロジェクト)の結果を紹介した。 展覧会前期(3月24日~5月6日)では、国内で所蔵される貴重なファン・ゴッホの初期作品(油彩画2点)と、彼が多大な影響を受けたジャン=フランソワ・ミレーの農民画(版画2点、パステル画1点)を展覧し、ファン・ゴッホがいかに労働者を崇高な対象として画布にとどめようとしたのか、その宗教感や自然感に迫った。
また展覧会後期(5月8日~6月10日)には、ファン・ゴッホが1910年以降の日本洋画界に幅広い影響を与えた痕跡を、岸田劉生や前田寛治、中村彝、中川一政らの作品とともに紹介した。 あわせて本館では、「生命讃歌~大地と人間~展」を同時開催し、藤田嗣治の大壁画《大地》をはじめ、偉大なる大地の上で繰り広げられる人間の営み-労働や憩い、祈りなど-を描いた近代日本絵画約50点を紹介した。
2011年
~描かれたベスト・オブ・ウッドワン展~
本 館:名品展 第一部
マイセン館:名品展 第二部
ウッドワン美術館開館15周年記念展の第2弾として、「どれもが名作、何度も感動」をキャッチフレーズに、当コレクションの中から精選した近代日本絵画約70点を一挙に展覧した。
展示作品の日本画は、横山大観《霊峰不二》、安田靫彦《森蘭丸》、小倉遊亀《夏の客》など約35点。洋画は、岸田劉生《毛糸肩掛せる麗子肖像》をはじめ、高橋由一《官軍が火を人吉に放つ図》、黒田清輝《木かげ》、青木繁《漁夫晩帰》、佐伯祐三《パリの裏街》など約35点。また、ファン・ゴッホ《農婦》も同時公開した。
本 館:名品展 第一部
マイセン館:名品展 第二部
花の画家として知られる中島千波画伯は、1945年長野県に生まれ、東京芸術大学在学中より院展を舞台に作品を発表し、1979年には山種美術館賞展で優秀賞を受賞、1995年にはパリ三越エトワールで個展を開催するなど、国内外で活躍する現代日本を代表する画家の一人です。
身近な花を繊細華麗に描いた花鳥画が有名ですが、1999年から2003年にかけては、週刊朝日に連載された宮尾登美子著『平家物語』の挿画全201点を手がけ、壮大なスケールの歴史絵巻を見事に描き表して新境地を切り拓きました。
本展は、中島千波画伯の生まれ故郷、長野県小布施にある「おぶせミュージアム・中島千波館」のご協力により、宮尾本『平家物語』の挿絵原画約30点をはじめ、初期のシュールレアリスム作品から、深い精神性を湛えた人物画、みずみずしく現代的な花鳥画の数々を展覧いたしました。
本 館:花鳥風月展
マイセン館:美人画にみる四季の美展
本館では、「花」・「鳥」・「風」・「月」という4つのテーマのもと、東洋の伝統を踏まえつつ独特の発展を遂げてきた近現代の花鳥画や風景画など51点を精選して展覧した。日本古来より今に受け継がれる「花鳥風月」の伝統。
それは自然の美しい風物や、風雅な情趣を楽しむことを表す。自然豊かな日本の風土では、四季折々にうつろいゆく風物や自然の営みに美を見出し、数多くの優れた美術作品が生み出されてきた。「花鳥風月」とは、日本人の自然に対するさまざまな見方や情報が詰まったまさにイメージの宝庫のようなものといえる。
また、マイセン館では、美しい女性の姿に自然や季節の情趣を託して描かれた人気の美人画13点展覧した。
~木を愛すふたつの心~
マイセン館:ウッドワン名作選
~春を寿ぐ絵画展~
本館では、「木」の強さやぬくもりを愛し、「木」を素材に独自の美を確立した二人のアーティスト、棟方志功と籔内佐斗司を紹介した。二人の間には半世紀もの隔たりがあるものの、同じように、木を愛し、生命の象徴である「木」を創造力の源としながら、それぞれ個性豊かな独自の世界を築きあげ、国内のみならず世界中で高い評価を受けている。本展では、二人の芸術家によって新たな生命を吹き込まれ、唯一無二の輝きを放つ木の芸術70点を展覧した。
また、マイセン館では、当館収蔵品の中から春にちなんだ絵画として、上村松園や安田靫彦ら近代日本画家の作品を10点展覧する「ウッドワン名作選~春を寿ぐ絵画展」を同時開催した。
2010年
うるわしのマイセン展
マイセン磁器誕生300年を記念して、ヨーロッパ磁器の最高峰と崇められるその魅力を、当館収蔵のマイセンコレクション約100点によってバラエティ豊かに紹介した。
本館では、マイセン磁器鑑賞のポイントを、東西の自然観や人物表現を比較しながら分かりやすく展示。また、マイセン館では、18世紀から20世紀初頭までの様式変遷を辿りながら、東洋趣味、ロココ、新古典主義、歴史主義と、時代の好みを取り入れて発展したマイセン磁器の美の真髄に迫った。
本 館:美術の中のどうぶつたち
マイセン館:招福どうぶつ園~福をよぶ動物たち~
子どもから大人まで楽しめる鑑賞入門の展覧会・第5弾として、美術の主題として欠かすことのできない「動物」をテーマに展示を行った。ペットや家畜としてわたし達の生活を支えてくれる動物たちや、自然の中の動物たち、日本にいる動物や異国の動物、何かを象徴するために描かれた動物たちなど、4つの小テーマに沿って彫刻7点、絵画59点を紹介。
また、展覧会に関連し、展示作品のぬり絵、クラフト教室、ワークショップ、親子を対象とした作品解説ツアーなどを開催し、多くの方に美術館を楽しんでいただけるきっかけとした。
マイセン館:洋画ベスト 10!
本館:日本画ベスト 10!&コレクションあれこれランキング
2009年度に行った「来館者による人気投票」の集計結果にもとづき、収蔵品の中から、近代日本絵画を中心に、特に人気の高い作品を選んで展示した。洋画と日本画のそれぞれのベスト10や、人気の画家たちの作品、また、幅広い支持を集めたジャンルなどのテーマ別と、選外作品から「ぜひ見ていただきたい」学芸員一押しの作品を展覧。
また、コレクションの新たな魅力をご紹介するギャラリーツアーやイベントをはじめ、「もっと好きになるウッドワン美術館」をテーマに様々な企画し、来館者の方に収蔵品をより身近に感じていただけるきっかけとした。
2009年
~松園・清方・深水を中心に~
古くは平安朝の源氏物語絵巻から、近世の浮世絵にいたるまで美術のテーマとされてきた「女性の美」。後に一つのジャンルとして江戸期に発展し、明治末期に百花繚乱の時代を迎えた「美人画」の世界を、官展を主な舞台に活躍した上村松園、鏑木清方、伊東深水らの作品を中心に紹介。
その他、伊藤小坡をはじめ、橋本明治、横尾芳月、森田曠平らの個性的な美人画の数々を展示し、繊細かつ華やかな美人画の世界を堪能できる内容とした。
籔内佐斗司展~袖振り合うも多生の縁~
鑑賞入門の第 4 弾として、当館の収蔵作品を「美術作品とともに暮らす」という視点で展示。屏風や掛軸、また作家こだわりの額縁など絵を飾るためのかたちに着目したり、アール・ヌーヴォーを代表する工芸家エミール・ガレの家具を絵画作品とともに展示し、美的生活空間を演出。 自分の家に飾るなら・・・そんなことを想像しながら、楽しむ展覧会とした。
また、マイセン館では平成の仏師・籔内佐斗司の作品世界と、国の重要文化財である伝周文《四季山水図》を紹介する、「籔内佐斗司作品展 ~袖振り合うも多生の縁~」を同時開催した。
ウッドワン美術館名作選`09春季
当館収蔵品の中から名品を選りすぐりながら、近代日本美術における人物表現の多様性をご紹介する内容。マイセン館では、岸田劉生の《毛糸肩掛せる麗子肖像》をはじめ、後期印象派の画家ファン・ゴッホの《農婦》、ルノワールの婦人像など、館蔵品の中でも特に人気の高い作品を一挙に公開した。
また、本館では、「見られる身体」をテーマに、歴史画や美人画、裸体画におけるしぐさやポーズ、身装などに注目しながら、上村松園や片岡球子らの作品をご紹介。「見る」私をキーワードとした自画像・肖像コーナーでは、藤田嗣治や三岸好太郎らが他者の姿に自己投影して描いた作品などを加え、画家の深遠な内奥に迫ることを目的とした。
2008年
- 薩摩焼展 -
- ウッドワン名作選 '08秋季 -
400年以上もの伝統をもつ薩摩焼の中でも、19世紀中ごろから幕末明治期の作品・約90点を展示。
薩摩焼は幕末の才女・篤姫の故郷で生産された焼き物であり、篤姫の生きた時代(幕末明治期)に飛躍的な発展をとげる。薩摩焼の隆盛は、篤姫の義父・島津斉彬(1805-1858)がすすめた殖産興業政策の成果でもあり、斉彬没後も引き継がれた努力が実を結び、「薩摩焼」は海外で高く評価され、日本を代表するブランドとしてゆるぎない地位を得ることになった。本展は、これらの薩摩焼を中心に薩摩金襴手の高度な技術、優れた芸術性を紹介した。
-ウッドワン名作選’08-
-ルノワールを中心に-
目には見えないものの、わたし達の生活にごく身近で、季節の風物としてもとても親しみ深い存在の「風」。
本展は、作中の風景や人物表現の中に、その「風」が運ぶ奥深い情趣を感じていただくことを趣旨とした。
「四季の風」、「海の風」、「異国の風」のテーマを設け、それぞれのテーマに沿って作品を紹介。作品横には、作品のイメージを膨らませる俳句や短歌などを掲示し、観覧者の方にも一句詠んでいただくコーナーを設けた。展覧会期間中には、「風」にちなんだコンサートやクラフト体験教室などのイベントを開催。
-風の色、風のすがた展-
-ウッドワン名作選'08 春季-
2009年度に行った「来館者による人気投票」の集計結果にもとづき、収蔵品の中から、近代日本絵画を中心に、特に人気の高い作品を選んで展示した。洋画と日本画のそれぞれのベスト10や、人気の画家たちの作品、また、幅広い支持を集めたジャンルなどのテーマ別と、選外作品から「ぜひ見ていただきたい」学芸員一押しの作品を展覧。
また、コレクションの新たな魅力をご紹介するギャラリーツアーやイベントをはじめ、「もっと好きになるウッドワン美術館」をテーマに様々な企画し、来館者の方に収蔵品をより身近に感じていただけるきっかけとした。
2007年
収蔵名品展 -冬季-
マイセン館の「いろいろアート術~アンディ・ウォーホルを中心に~」では、収蔵品の近現代アートの中から、パブロ・ピカソの初期銅版画の代表作《貧しき食事》や、ジョアン・ミロ、アンディ・ウォーホルらの版画作品、絹谷幸二のフレスコ画や有元利夫のテンペラ画など、素材・手法にこだわった海外・国内の9作家12点の版画・絵画作品を展覧した。
また、本館では「収蔵名品展-冬季-」を同時開催。当館日本近代絵画コレクションの中から、冬から春にちなんだ季節感ある作品を中心に、日本画と油彩画、約55点を紹介。
-光と影の饗宴展-
-ウッドワン名作選`07秋季-
絵画の中に表れた様々な光と影の表現に着目し、いろいろな側面から近代日本絵画にアプローチを試みた展覧会。日本画においては、「雪月花」や「花鳥風月」をキーワードに、日本的な光と影の表現を探り、絵画の中に表れた日本人の自然観や美意識に注目。
また、洋画では、「人物像(裸婦画)、風景画における陰影表現」といったテーマを掲げ、光と影を技術的な面から捉えるとともに、「作品に表れた画家の心象」というテーマを加え、人の心模様を映し出した陰影表現―光と影―を見ることで、個性的な画家たちの内面に迫った。また、あわせて、藤田嗣治の幅9mを超す大壁画《大地》の特別公開を行った。
-レッツ・時間旅行展-
-ウッドワン名作選`07夏季-
絵画鑑賞入門の第2弾として、絵の中の「時間」をテーマに作品をじっくりと「観る」展覧会。
①「季節・時刻」、②「人物の年齢」、③「感じる時間」、④「作者の時間」の4つのテーマを設け、各作品を展示。展示作品それぞれに、絵の中の季節や人物の年齢を問うキャプションを掲示。ヒントを記すとともに、それぞれの展示室入り口に答えと解説文を記した解説シートを設置し、絵の季節や、人物の年齢を予想しながら見ていただくことで、クイズ感覚で楽しみながら鑑賞のコツが身につくように配慮した。
また、アートかるたやガイドブックを使って、当館学芸員が展示作品について分りやすく解説する絵画鑑賞ツアーも、盛況をおさめた。
-日本美術史を散歩しよう-
-ウッドワン名作選-
美術史って難しい…。
特に、約140年の短い歴史の中で、時代と共に劇的な変遷を遂げた明治維新以降の美術史に対するそのようなイメージを変えるべく、明治から昭和前期に活躍した巨匠といわれる画家、約50名の作品を紹介しながら、日本近代の美術史の流れをやさしく解説。美術史に親しんでいただくため、画家の顔写真や、美術の流れをチャート式にまとめたパネルなどを用い、わかりやすい展示とした。横山大観をはじめ村上華岳、黒田清輝や岸田劉生らの作品を紹介。
2006年
「新ニッポンの表現展」では、国内外で熱い注目をあつめる二人のアーティスト、籔内佐斗司(やぶうち・さとし/1953-)と筧本生(かけい・もとなり/1951-)を取り上げた。
出品作品は、「童子」をモチーフにした籔内の木彫・ブロンズ作品約20点と、パリのエスプリ漂う筧の人物画5点。一度見たら忘れられない…、不思議で楽しいアートの世界を紹介。 同時開催の「近代日本絵画収蔵名品展-冬季-」では、ウッドワン美術館日本近代絵画コレクションの中から、新しい年を寿ぐよ うな新春にふさわしい作品や、春夏秋冬の季節感ある作品などを中心に展示。
開館10周年を記念し、館蔵品の中でも特に人気の高い作品や、これまで紹介しきれなかった作品を一堂に展覧。マイセン館の特別展示室ではルノワール《オレンジを持つ少女》の初公開をはじめ、ファン・ゴッホ《農婦》など、コレクションの逸品を紹介した。
本館では、同一テーマに対し、複数の画家の作品を比較展示するほか、明治以降の日本絵画に影響を与えた西洋の画家と、彼らに影響を受けた日本人画家の作品を並べて紹介。くらべて見ることで、個々の作品の特徴、表現の多様性、ひいては通底する日本固有の美意識といったものを再発見できる展覧会とした。
「画材」や「マチエール(絵の表面の質感)」、「色」といった絵画の諸要素に着目。本館では、この3つのテーマに沿って展示を行なっており、各テーマに着目し、作品をいつもより時間をかけてじっくりと見ることで、新しい絵画の魅力を再発見していただくことを目的とした。
マイセン館では国の重文、伝周文「四季山水図」など、巨匠たちの作品を紹介。また、小さなお子様にも楽しんでいただける絵画鑑賞ツアーを開催。単眼鏡やライト、探検ブックを使って、展示作品について分りやすく解説。
-日本近代画家たちのまなざし-
二つの絵画企画展示からなる本展では、各画家の個性に富む画世界を紹介。「ウッドワン美術館名作選 '06 春季」では、館蔵品の中から厳選した日本近代絵画の逸品を特別公開。
「文化勲章受章作家による珠玉の絵画展」では、文化勲章受章作家約40人を選りすぐり、それぞれの画家の極めて代表的な作品の数々を、エピソードを交えて展示。
2005年
マイセン新収蔵品展&エミール・ガレ 作品展
ウッドワン美術館の日本の近代絵画コレクションの中から、冬から春、季節にちなんだ作品を中心に、日本画27点、油彩画29点を展覧。冬から春への季節の移り変わりゆく様を、絵画の中で紹介。
当館初公開となるマイセン磁器約10点と、2006年版カレンダー掲載作品であるエミール・ガレの作品6点を一堂に展覧。マイセン磁器の華やかさと、ガラス作品の煌きをご堪能していただくことを目的とした。
館蔵品の中から、山や水辺、旧跡、街角など風景を題材とした絵画作品約50点を精選し展覧。
展示作品はいずれも、画家たちの透徹した眼差しと真摯な姿勢によって、多彩な風景の魅力が絵画化された佳品。山や川など侵しがたい天然の美だけでなく、人間の生の痕跡である旧跡や都市の景観美を表現した作品を紹介。
当館初公開となる新収蔵品約20点を含む、日本の近代絵画50点余を一堂に展覧。主な新収蔵品である円山応挙《老松太藺鯉魚図》は、江戸時代に円山派のリーダーとして写生画の基礎を築いた円山応挙の代表作の一つ。二幅対の本作品において、右幅に古木の松を仰ぐ鯉を、左幅には太藺のもとで悠々と泳ぐ鯉を写実的に描き、自然を愛した応挙らしい繊細な情緒が感じられる。
また、ルノワールの《花かごを持つ女》・《婦人習作》を、マイセン館にて特別公開。
~近代日本の名画と幻のガレ・コレクション初公開~
花をテーマに、絵画とガラスの2つの企画展を開催。ガラス企画展では、エミール・ガレの新収蔵品を中心とするガラス作品61点により多様な花の表現を紹介。
絵画企画展では、花を主題・モチーフとする近代日本の名画46点を展示、日本人の自然観や美意識に根ざした、さまざまな花の表現を紹介した。また、岸田劉生の麗子像、ファン・ゴッホ《農婦》を同時公開。
2004年
ウッドワン美術館の日本の近代絵画コレクションの中から、冬から春、季節にちなんだ風景画や2005年の干支である鳥を画題とした動物画を中心に、日本画27点、油彩画31点を紹介。新春の息吹を感じ取っていただけるような展覧会とした。
絵画の中に表れた様々な光と影の表現に着目し、いろいろな側面から近代日本絵画にアプローチを試みた展覧会。日本画においては、「雪月花」や「花鳥風月」をキーワードに、日本的な光と影の表現を探り、絵画の中に表れた日本人の自然観や美意識に注目。
また、洋画では、「人物像(裸婦画)、風景画における陰影表現」といったテーマを掲げ、光と影を技術的な面から捉えるとともに、「作品に表れた画家の心象」というテーマを加え、人の心模様を映し出した陰影表現―光と影―を見ることで、個性的な画家たちの内面に迫った。また、あわせて、藤田嗣治の幅9mを超す大壁画《大地》の特別公開を行った。
当館初公開の日本画約15点、油彩画約20点を一堂に展覧。
主な新収蔵品である梅原龍三郎《霧島》は、梅原芸術を代表する風景画の一つに数えられる。手前にススキの穂波や紅葉した樹木を描きこみ、山並みの彼方に美しい桜島の姿をとらえた本作品では、雄大な自然が、力強く、それでいて柔らかな叙情性を込めて描き出されている。他にも、速水御舟《荒海》などを展覧。
館蔵品の中から、人間がモチーフ、テーマとなっている絵画作品約50点を精選し紹介。生命を尊び、人間の在り様とその営為を描き伝えることは、私たち人間の普遍的なテーマであるといえる。描かれた「人」を通して、今一度、人間存在について想いを巡らし、それぞれに「人間像」を紡いでいただくことを目的とした。
2003年
ウッドワン美術館の日本の近代絵画コレクションの中から、冬から春、季節にちなんだ作品を中心に、日本画27点、油彩画27点を展覧。新春の慶祝の気分を伝える作品や、一足早く芳しい春の香りをお届けする作品を紹介。
このほか、和装の美を描出した作品などを展覧。風景や花、衣装などに、豊かな季節の情趣を味わっていただけるような展覧会とした。
四季の変化に富んだ日本では、古来より自然に対する豊かな感受性が育まれ、季節を題材とする芸術文化が発展。季節の情趣を意識した絵画作品は数多く制作され、私たちの自然観に深く関わってきた。
本展では、近現代に制作された四季を彩る絵画作品約60点を展覧。四季の情趣をより深く味わっていただけるように、春夏秋冬、各季節の作品を4つの展示室に分けて紹介。
日本では古来、木肌の温もりや物としての深み重みを生かして木彫や版画が制作されてきた。また、その姿形の美しさ、力強さ、神秘性がしばしば絵画化されてきたほか、古くから支持体としても用いられている。
本展では、木彫作品約20点を展示。また木理をいかした力強い版画で知られる棟方志功の作品を公開。絵画では、木板を支持体として描かれた作品のほか、花木や林、森を主題とした作品を展覧。
館名変更1周年を記念し、ウッドワン美術館絵画コレクションの中から、明治から大正・昭和にかけて活躍した個性豊かな53人の画家たちの作品約60点を展覧。近代を生きた画家たちが、それぞれに築き上げた個性あふれる画世界を紹介。
また、新収蔵のフィンセント・ファン・ゴッホ「農婦」を本展で特別公開。
2002年
冬から春、季節を彩る作品を中心に、当館初公開作品8点を含めた約50点の館蔵品を展示。
美人画は理想化された女性像を表したもので、日本独特の絵画ジャンル。明治の末頃から美人画は隆盛、伊東深水、上村松園らが活躍する。本展では、浮世絵の伝統を受け継いだ美人画から、近代的な発展を見せた日本画作品まで、さまざまな女性像を展覧。
一方、洋画では、理想的な女性像だけではなく、日常生活の中の女性が多く描かれている。日本人女性をモデルにその特徴的な肌質を表現する画家、浮世絵の様式を取り入れる画家など、多様な展開を見せた日本洋画における女性像も紹介。
力強く生きる人間と、人々の暮らしが息づく自然の情景をモチーフとした日本の近代絵画約50点を紹介。
展示作品には、人間と自然の密接な関係が映し出されている。これらの絵画作品に表わされた人々の姿は、私たちに、自然と人間の根源的な結びつきを思い出させてくれ、また、人間と自然の関わり、生活の息遣いは、人物が描かれていない風景画からも感じ取ることができる。自然に向かう私たちのまなざしを見つめ直すきっかけとなるような展覧会を目的とした。
画家の優れた創造性に注目し、館蔵品から精選した日本の近代絵画約50点を展示。
本展では、創造の源となった主題ごとに作品を展覧。それぞれの主題が画家によってどのように形作られ、またそこに画家の「創造する力」がどのように働いているのか、出品作品を通じてご覧いただくことを目的とた。
2001年
2000年
1999年
-世紀末・ガラス芸術の精華 -
1998年
1997年
1996年

休館日
-
- 休館日は展覧会ごと設定されております。詳しくは、開館日カレンダーをご覧ください。
- 各展覧会前後は展示替えのため数日間休館します。
- 冬期休館(2025年12月15日(月)~2026年3月19日(木))
カレンダー
■休館日 ■イベント日
2025年度展覧会日程
※展覧会の内容、会期、休館日は変更になる可能性がありますので、詳しくはホームぺージや公式SNS等でご確認ください。
one’s art プロジェクト
3月15日~ 3月30日
わたしのアート
~つくることは生きること~
春季展 4月5日~ 6月15日
よそおい、かざる
~絵画、工芸、ガラスの装飾美~
夏季展 6月21日~ 9月7日
~渡辺おさむスイーツアート~
お菓子の美術館
秋季展 9月13日~ 12月14日
~アール・ヌーヴォーの華~
アルフォンス・ミュシャ展